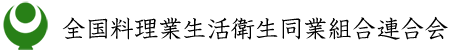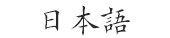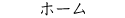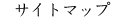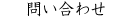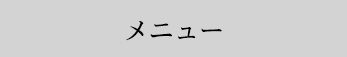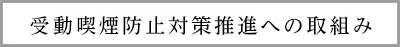夏が旬の食材
初夏のしつらい
<5月>
●新茶が薫る夏のはじまり
五月二日は八十八夜。立春から数えて八十八日目にあたります。昔から「八十八夜のわかれ霜」という季語があるように、これ以後は霜がなく、農作業や茶摘みを始める時期とされています。「夏も近づく八十八夜」と、幼い頃うたった「茶摘み歌」も懐かしく想い出されます。

この新茶を壷に入れて封をし、秋まで熟成させますと豊潤な香がより高くなります。その葉茶を臼でひき、お茶を点て、お客様をもてなします。この、新茶をはじめて使う茶会の行事を、茶の湯の世界では「口切りの茶事」といっています。灘や伏見の酒蔵で新酒が蔵出しされるのも、このころです。陽気がよくなると、魚市場にも活気が出てきます。品物も豊富になり、初鰹も出回ります。とくに、白身の魚がおいしくなります。
鯛はもちろん、こち、ふっこ等。あないめを焼霜にし、梅肉を添えれば、季節感豊かな向附ができあがります。そして、筍やそら豆もこの時季こそが旬で、味わい深くなってくるのです。
●焼き目がポイント「石やき豆腐」
今月は「石やき豆腐」と呼ばれるお椀を紹介します。
まず木綿豆腐を、表面をみがくように薄く切り落とします。それを四ツ切りにし、バーナーかガスレンジの口火管を使って、六面ともところどころ濃淡の変化をつけて丁寧にやきめをつけます。湯抜きにしてから、少し濃い目の椀づゆで弱火でコトコトと煮て、味をふくませます。
次に、五、六匁の活海老を用意し、頭を取り、ぐるむきにし、背びらきにしてわたを取ります。二、三か所、庖丁目を入れて薄塩をふり、塩がなじんだころあいに、海老の味が逃げないよう、葛打ちにします。
ちしゃとう、うど、人参は皮をむいて、短尺に切りそろえます。これは昔、節句の時、飾られた紅、白、緑の菱餅にみたてるのです。
青味はつる菜、吸口は花柚子。花柚子とは柚子の花の蕾です。少し硬いようでしたら、指で軽く押すと割れ、ほのかな香りがただよいます。汁は、陽気もよいので清汁がよいでしょう。
<6月>
●料理店も衣替えの季節
東京では、雨の日が多く、うっとうしい日が続きます。六月といえば、衣替え。うちの店でも、制服のある学校や職場と同じように、仲居さんが無地で淡い色の着物に衣替えをし、気持ちを改めてお客様をお迎えするようにしています。
今月の花木は額紫陽花。ふつうの紫陽花に比べて地味な雰囲気の花ですので、日本間によく合います。他には藤、花菖蒲、名残の燕子花。これらの花は掛軸や額装の絵に描かれている場合が多いので、重複しないようにしたり、花入を置く位置に気を配ります。

草花では桔梗、半夏生、そして可憐なほたる袋が咲きはじめます。
これらを龍の花入に生ければ、より涼しげに映ります。
六月一日から鮎が解禁になり、稚鮎、若鮎として料理屋さんの献立にのるようになります。この時季、さしみでも焼物でも白身の魚を使うことが多くなります。
器も底が浅く、染付でも模様が少ないものの方が、盛りつけた料理が涼しげでよく引き立ちます。冬場は見た目に暖かみがあり保温力もある厚めのお椀を用いましたが、六月くらいからお椀もだんだん薄手のものを使うようになります。
●初夏からがおいしい「沢煮椀」
なかなか食欲のわきにくい時ですので、今月は少し香辛料をきかせたお椀もりにしてみました。
まず、あげられるのが沢煮椀。沢煮椀は、豚の脂身と野菜を使ったお椀で、南蛮渡来のものと思われていますが、本来は漁師が漁に出たときの保存食として、持ち合わせた塩漬けの肉と野菜を使い、汁にしたところから生まれたといわれています。
作り方を簡単にご紹介いたしましょう。
あらかじめ薄塩をした豚の脂身を細く切り、だし汁でサッと煮て、水気をきっておきます。昆布と鰹節の椀づゆに、水煮にしたうど、たけのこ、椎茸、脂身、ささがきぼごうの順に入れ、椀づゆがひと煮立ちしたら、味醂を数滴加え、三つ葉を入れます。そして最後に忘れず、こしょうをふりいれます。ここがポイントです。
コツは椀づゆに浮かべたとき、きれいにみえるように、具を同じ寸法に細く切ることと、手早く煮上げることによって豚の脂身もサラッとした口あたりに仕上げることです。 この沢煮椀は、初夏から秋にかけてがおいしいといわれていますが、一年中献立にのせ、”名物”としているお店も多くあります。
殊に銀座一丁目の「金兵衛」さんは有名です。二代目のご主人、高井田敬一さんにお話をうかがうと、お父様の代から一年のうちごく一時期をのぞいて、沢煮椀を出しているそうで、うちの店と共通のお客様が、「あそこの沢煮椀は昔とちっとも変わらない味だ」と評していました。その名物に満足すると共に、その店の健在なことを再確認するわけです。
『いろどり』 24号より 別府 克巳(竹葉亭 主人)
鮎(あゆ)
アユは山の幸? といぶかる読者もいらっしゃるかも知れません。
アユは谷あいや渓谷の川に生息する川魚の王者で、我々日本人はアユに多大な思い入れを持っています。何にでも油を通して味わう西洋人には、塩で焼くだけの淡白なアユの美味しさを感じてもらうのは難しいことでしょう。
アユには天然ものと養殖ものがあることは言うまでもありませんが、その違いはどこにあるのか、少しご説明しましょう。まずスタイル。天然ものはスラッとしてどこか精悍な感じさえします。養殖もののアユは、ずんぐりむっくりしたおデブさん。色も養殖ものは黒ずんでいて、天然ものは脂びれのところがピンク色をしています。また顔つきもどことなく異なり、自然の厳しさを知っている天然のアユたちは、なんとなく賢そうな気さえします。
 「いろどり」第7号より 出井 宏和
「いろどり」第7号より 出井 宏和
もっともこんな違いより、値段をみれば一目瞭然で、天然ものは小型でも養殖ものの三倍以上の卸値がつきます。ちなみに1kgあたり養殖ものは千二百円なのに対し、天然ものは中型は一万三千円、大型になりますと二万円、という格段の違いです。
アユは捕れたてがなにより、しかも簡素に、つまり塩のみをつけて焼くというのがいちばんおいしい頂き方です。天然のアユは香魚といわれ、たいへん良い香りを放ちます。この香りの秘密は川の石に付着する藻を餌にしているからです。いわばアユはクロレラ食をとっているのです。一方の養殖アユは香りがまったくしません。
アユの名産地、岐阜県の長良川では、川底にサッカーボール大の石がごろごろところがっています。私もためしにこの石の藻を食べてみましたが、ただ青くさいだけ。しかしアユにとっては食の宝庫。石についた藻を、体を横にして唇のわきでそぎ取るようにして食べます。川面にキラリとアユが光るのはこの一瞬で、横になったアユの腹が光るわけです。
アユは魚のなかでいちばんたわいもなく死んでしまう魚で、たいへん傷つきやすい魚です。卸値で最も高値なのが友釣り、次いで網で捕ったもの、そして鵜飼で捕れたものがいちばん安くなります。長良川の鵜飼の行事は、千二百年もの歴史をもつ由緒あるアユ漁法です。鵜のくちばしはやすりなどで削って丸くしていますが、どうしてもくわえる時に傷がついてしまい、卸値が安くなるのです。
日本全国すべてに天然アユは供給できないので、養殖ものに頼らざるを得ません。全国五か所の種苗センターで養殖されていますが、取引が重量単位になるので、どうしても太りぎみになってしまいます。アユは水温が上がるといくらでも餌を食べるそうです。ですから水温を十五度以下にし、出荷前の二~三日は絶食をさせると、精悍なひきしまったアユができるといいます。ただし香りはまったくつきません。天然のとれたてのアユは姿造りにしたり、一夜干しや雑炊にしたり、いろいろなバリエーションがあります。しかし本場岐阜県では、単純この上ない塩焼きが最上、というのが定説になっており、私もまったく同感です。
鱧(はも)
京都の一大イベント・祗園祭に欠かせない食の主役がハモです。京都の台所・錦小路の市場にハモのない魚屋はありませんし、主婦たちは必ずハモを買っていきます。古都京都に夏の訪れを告げ、祗園祭をいっそう盛り上げるのがハモなのです。
ハモの語源は「食む」(はむ)から来ているといわれるように、ハモは何にでも噛みつく獰猛な魚です。この強さが味わい深さの理由とされています。また、生命力が強く水から揚げても長時間生きています。その昔、京都に運ぶ途中にハモが荷籠から跳ねだし、あとから通りかかった者が泥まみれになってもまだ生きているのを見て、「京都のハモは山で捕れる」と言った----という笑い話があるほどです。
 「いろどり」 第41号より
「いろどり」 第41号より
関西の料理人はハモを扱えなければ一人前とは言えません。頭から尾の方に並んでいる無数の松葉のような小骨をさばくのを「ハモ切り」「骨切り」といいます。大きくて重い片刃のハモ包丁で、一ミリメートル間隔でシャッシャッとリズミカルな音をさせながら皮一枚を残して切っていきます。関東でハモが定着しないのは、骨切りが面倒くさく、気の短い関東人には向かないためという説もあるとか。
ハモは、鰻の蒲焼のようにタレをつけて焼いたもの、ハモ寿司、お吸い物のわんこ、切りおとしなど、さまざまなバリエーションで関西に定着しています。とくに湯どおししたハモの切りおとしは、まるで白い牡丹のようで美しく、これを梅肉や梅酢でいただくと、おいしくていくらでも入ります。
鰻(うなぎ)
養殖うなぎは、養殖場で人工孵化した稚魚が大きくなったもの、と思っている方が多いのではないでしょうか。
実は、現在の技術では卵を孵化させることはできても、孵化した稚魚を育てることができません。何を食べさせたらいいかわからず、どんな餌を与えても食べないのです。目下盛んに研究中ではありますが、今のところ、うなぎの養殖は、まず天然うなぎの稚魚(しらす)を捕るところからはじまるのです。
うなぎは海で産卵し、河口から川を上り、再び産卵のために海に戻っていきます。十一月ころ、産卵のために海に下ろうとするうなぎを「下りうなぎ」と言いますが、これは産卵前の、いちばん脂ののった最高においしいうなぎです(資源保護のためには下りうなぎはあまり捕らないほうがいいのですが・・・・・・)。
 「いろどり」 第23号より
「いろどり」 第23号より
うなぎが産卵する場所はというと、どうやらフィリピン沖あたりらしいのですが、細かく特定はできていません。孵化したしらすは北上し、九州から浜松、北は銚子あたりまでに到達し、河口から川へ上っていきます。このあたりで、しらす漁が行われます。
しらす漁は十二月に解禁され、三月いっぱいまで行われます。このころになると体長五・五cmほどに成長しています。しらすの捕れる量は、ここ数年で激減しており、しばらく高値が続いています。今年も史上最悪といわれるほどの不漁で、一kg(約五千匹)が何と百万円という値段。養殖うなぎが卵を産めばいいのですが、今のところ、そういった話は聞いたことがありません。養殖池の中では産卵のための条件が整わないようです。
しらすを養殖池に放すわけですが、この大きさにまで育っていれば、稚魚はイワシの粉を主な原料とした餌で、どんどん大きくなっていきます。
土曜の丑の日に出荷するには、おそくともその年の一月二十五日ごろまでには養殖池に放さなければなりません。池に放たれてから約半年で大人になる(成鰻する)ものを、「新子」といいます。早めに大きくなった分、やや味は薄めのものがあるかもしれません。もう少しゆっくりと、秋口から初冬にかけて成鰻したものは、夏場のうなぎより脂ものって、締まりもよく、味も最高です。やや時間をかけて成鰻したものを「ひね子」と言います。
うなぎというと夏のイメージが強いかもしれませんが、天然ものでも養殖ものでも、うなぎは秋口から初冬にかけてがいちばんおいしいのです。
うなぎを順調に発育させるには、水温を常に約二十八度に保たなければなりません。少しでも水温が下がるととたんに餌を食べなくなり、成長が悪くなってしまいます。
柏餅、粽(ちまき)
現在では男子というより子どもの日として国民の祝日となり、昔ながらに縁起ものの柏餅や粽(ちまき)を食べて祝います。京阪地方では初節供に粽を作り、二年目からは柏餅を作って食べます。粽には三角形か円錐形の笹巻のほかに 小豆や味噌を入れた丸い笹団子の粽があります。粽の起こりは、中国春秋戦国時代の楚の国の屈原がねたまれて失脚し、汨羅の川に身投げしたのを悼み、楚人(姉という説もある)が米を竹筒に入れ、楝の葉でくるみ、あや糸で結んで投げ入れたというのが定説のようです。
端午の節供料理には粽に見立てた粽ずしが用いられます。関西風の料理ずしといわれ、甘味をひかえたすし飯に酢〆の白身魚や海老を抱かせて三枚の笹の葉で包み、藺で巻きしめたものです。粽ではありませんが鮨の系統に笹巻ずしがあります。
 「いろどり」第36号より
「いろどり」第36号より
鮎や鰺、鱚、小鯛、こはだなどのそぎ身を酢〆にしてすし飯と熊笹で巻いたもので、小骨を抜くのに毛抜きを用いたことから毛抜きずしともいいます。
笹は防腐、保存性にすぐれた素材ともいわれています。江戸名物笹巻毛抜鮨の老舗は現在でも神田御茶ノ水にあります。五月の若葉を用いる柿の葉ずしは、塩鯖のそぎ切りをすし飯と合わせて柿の葉で包み、桶などの容器に入れて重石をして一昼夜おいたものです。奈良県の名物料理にもなっています。
今日の会席献立にも伊勢海老具足煮、鯛兜焼き、兜煮、矢羽根羮、矢羽根蓮根、的穴子、盾鳥賊、弓牛蒡、吹き流し豆腐など、節供見立てのものが供されます。
地方によって祝善には菖蒲酒がつき、鯛や鰹=勝男、鯉などが用いられ、菖蒲湯に入る風習が広く残っています。
柏餅といえば、吾が子の初節供に武者人形も買えないのんべえの父親が、叔父が恵んでくれた人形代を持って買出しに行く途中、仲間につかまり、気前よく振舞ってしまい、手ぶらで家に帰ると、叔父に柏餅をご馳走しますといって五布(いつの)ぶとんにくるまったという小咄を思い出します。
農村に育った筆者にとっての柏餅はぼた餅や団子と同様のお袋の味でもあります。上新粉であんを包み庭の柏の葉でくるんで蒸したものを、鯉のぼりを眺めながら頬ばる少年時代の姿が彷彿としてきます。
「目に青葉山ほととぎす初鰹」(素堂)の句は初物食いの江戸っ子が女房を質に入れても初鰹という信仰を作ったものですが、つかの間の五月も小満(万物が成長し陽気盛んに満ちる候)をすぎるともう入梅を迎える季節になります。
なごり筍
釜に湯を沸かしておいてから、裏山に筍を掘りに行く。田舎のお嫁さんは、「赤子泣かせても筍を先に釜に入れろ」と教育された。掘ってからどれだけ早く茹でるかが、筍の味を決める。一分一秒を争う時間の勝負だ。
筍の旬は一瞬だ。二~三日、極端にいうと一日で旬を過ぎてしまう。土が割れて筍が顔を出したときが、はしり。大人の手の巾くらいに伸びたときが旬。それから一日で二倍の大きさになる。手の巾二つ半分まで成長するとなごりとなる。なごりの筍はいちばん味がいいが、若干固くなる。
 「いろどり」2号より
「いろどり」2号より
筍には、時期を追って三種類ある。最初は五月になごりを迎える孟宗竹。産量が多く、ふつう筍というと孟宗竹を指す。次が真竹。そして最後は六月に旬を迎える淡竹。産量が少なく高価で最も美味しい。
茨城産の筍が、風味、歯ごたえ、旨みともに最高だ。が、値が高すぎて行き先はもっぱら高級料亭。庶民の手に入りやすいのは、鹿児島産、静岡産のものだ。
どんな筍でも、いつの筍でも、必ず調理する前にアク抜きをするのが原則である。アクとはエグみであり、エグみは味のうちに入らない。皮のまま、丸ごと(穂先も切らず切れ目も入れなくてよい)、米のとぎ汁かぬかを入れた水に唐辛子を加えて五時間くらい茹でる。そのまま一晩おいて翌日水にさらす。
十一、十二月頃、まだ土中三○cmくらいに埋まっている筍を掘り出したものを早掘り筍という。柔らかく珍しいだけの筍で、本来の旨みには欠ける。正月の重詰などに使う。はしりの筍は若竹椀、旬の筍は塩焼き、なごりの筍は煮しめがもっとも美味しい食べ方だ。塩焼きは、丸のまま塩を振りかけて串打ちして焼き、ポン酢で食べる。最高の酒の肴だ。煮しめには、かつを節をかけて木の芽をあしらう。木の芽のピリッとした辛さが筍の美味しさをひきたてる。
エダマメ
「ビールといえばエダマメ」と反射的に出るほど、エダマメはビールと相性のよい食べ物です。ビアガーデンなどで、同行した若い女性たちに「エダマメの育ったのが大豆である」とウンチクを傾けると「ウッソー」などという声が返ってきます。エダマメが未熟な大豆の一形態であることは案外知られていないのではないでしょうか。
大豆は他の豆類に比べ、タンパク質と脂肪が格段に豊富です。タンパク質含有量が全体の三五%、脂肪のそれは一九%、そして残りが糖分で水分がほとんどありません。この栄養豊富な大豆を、熱する直前に採って食べるのがエダマメですからおいしいはずなのです。枝についたまま食べるので枝豆といいますが、別名「アゼマメ」ともよばれました。
 「いろどり」4号より
「いろどり」4号より
枝豆や田毎の畦のつくり徳 格堂 という句が語るように、本来は田んぼの畦のわきに大豆を植えました。大豆の主根は地1mにも達することもあり、たくさんの分岐根を出し、この根に球状の根粒ができます。根粒には根粒菌というものが発生し、この菌が空気中の窒素を貯えて大豆の栄養源となります。大豆は世界的食品ですが、エダマメ状態で食べるのは日本人だけなのです。
大豆のルーツはシベリアのアムール川流域とされています。そもそもエダマメを生産し、これを嗜好品としていたのは東北、関東、新潟など関東以外でしたが、現在では全国的に生産されています。それだけエダマメが日本中あまねく定着した、国民的好物となったからでしょう。
なかでも静岡県・清水市駒越ではエダマメの温室栽培がたいへん盛んで、「駒」のブランドで出荷されています。この地は温暖な気候で太陽の光をいっぱい受け、水はけのよい砂地という立地条件にも恵まれています。温室メロンの技術にも精通しており、その伝統を生かしてエダマメ栽培が発展しました。苗を植えてから一か月で花が咲き、ふた月で実がなり収穫します。ですから年間三~四回栽培できることになるわけです。ちなみにこの実のなる温度も十五度です。生産時に最も気をつかうのが、「しみ」と「色」です。温度管理を誤ると霜がサヤの毛に付いて「しみ」ができてしまうのです。色も「サッポロミドリ」という鮮やかな緑色になるよう品質改良を重ねました。
清水のハウス栽培のエダマメが出終わり、七月になると今度はいっせいに露地ものが登場します。これは鮮度のよさが勝負。東京・築地で定評のあるエダマメは、埼玉県草加や新田の「ユキムスメ」、群馬県沼田の「天狗(錦秋)」などです。大阪では徳島県の「宝石」、岐阜県高山ものなどです。その他、出荷時期が遅く、あまり市場には出回りませんが、山形県庄内の「だだちゃ豆」、新潟県の「新潟茶豆」、兵庫県丹波の「黒大豆」などは、昔ながらの香りとコクのあるエダマメが味わえます。
夏=ビール=エダマメと連想しがちな我々には、エダマメの夏の食べ物としてインプットされています。現在では冷凍もので真冬でもエダマメを食べることは可能ですが、本当の旬は初秋なのです。
陰暦の九月十三夜の月見にはなくてはならないものとされており、十三夜のことを「豆月見」、エダマメのことを「月見豆」と呼び、九月下旬が最もおいしいとされていました。しかしこれは露地ものに限ってのことで、現在では上述したように温室栽培のおかげで六月にはすでにおいしいエダマメのテーブルを彩ります。
はちきれんばかりに張ったエダマメは、若い女性のジーンズ姿にも似た、若々しく瑞々しい弾力があります。塩茹でしたのを指ではさむとスポンと口の中に飛んできます。そしてほろ苦いビール。若さと人生の渋味を感じさせるこのカップルは、やはり日本の夏にはなくてはならない食のひとつです。
鮪
世界中で日本人ほど鮪好きな民族はいないでしょう。骨なし皮なし匂いなしの魚しか食べない今時の若者さえ、鮪にだけは寛容です。
なかでも日本人はトロが大好き。といっても大騒ぎして食べられるようになったのは戦後のことで、当時、脂肪分が不足していた日本人が栄養的に欲していたのがその始まりと推察されています。飽食の現代にあっては、少しずつトロ離れしているとも聞きます。
確かに脂身の多いトロなど、上品な食べ物とは言いがたく、以前は茶屋物(料亭用の魚)には使わなかったものです。今でも関西の料亭では、造り(関西の刺し身の呼称)といえば白身魚に限り、赤身はせいぜい脂身が少なく淡白なメジ(本鮪の子供)を使うぐらいです。トロは主にネギマ(鮪と葱のぶつ切りの鍋料理)として食されていました。カマ下の大トロなど二束三文で売り捨てられていたのに、今や本鮪のトロでキロ四万円もするのですから・・・・・・。
 「いろどり」13号より
「いろどり」13号より
鮪好き日本人の需要にこたえるべく、鮪漁船は今日も季節をわかたず世界中の漁場へと出漁していきます。遠洋鮪船の場合、一度出漁すると半年から一年は操業に明け暮れ、船の積載トン数の八割まで獲り続けるそうです。
遠洋の鮪は、洋上で零下六十度にまで急速冷凍させ(といっても二日かかる)、鮪の風味を損なわず品質を保ったまま日本まで運ぶことができます。この技術革新により、市場ではハワイ沖辺りで獲れる冷蔵ものより、遠洋の冷凍ものの方が歓迎され、値段も高いのです。
近海もののなかには、台湾鮪もあります。日帰りの出漁で帰路は航空便で運ばれるため、新鮮さでは引けをとらないのですが、手荒く扱われるためか内出血が見られ、その価値を下げているようです。
同じ近海ものでも、日本の近海鮪の雄は、三陸の鮪。しかし漁獲高が減り、そのせいか東京の築地市場ではボストン鮪が幅をきかせています。こちらも空路、飛行機で輸送され、新鮮そのもので築地に到着します。味もよいので、値段的には三陸ものを凌ぐ上物として取引されていままきす。それ故、アメリカの大西洋岸でもこぞって獲りまくり、年々品不足になってきました。
いずれにしても、持て囃されるからと、とめどなく獲るのは考えものです。特に遠洋漁業の冷凍鮪に多くの幼魚が混じっているのは問題です。近年盛んに言われるようになった資源保護の面からも、ある程度育ったもののみ捕獲すべきで、そうしないと大好きなトロが本当に食べられなくなる日がくるかもしれません。
とはいっても、老若男女を問わず鮪は日本人の大好物です。今後もずっと獲り続けられることでしょう。そこで近年、資源確保の試みとして鮪の養畜(養殖ではありません)がスペインで始まったのには大いに期待しています。無論、日本人が行っているのでしょうが、ハマチと同じ轍(餌による風味の損失という失敗)を踏まないように、ただただ祈るばかりです。鮪がなくなって困るのは、私たち自身なのですから。
ヤマイモ
とろろとして食べるヤマイモはヤマノイモともいう。ヤマノイモ科に属するが、その種類は約六〇〇もあるらしい。熱帯や亜熱帯、とくに中南米に多い。
日本では副食として食べるか製菓の原料とすることが多いが、熱帯地方では主食にしている。主成分の一つとしてデンプンを含むため、主食としてもじゅうぶん役立つわけだ。
日本で利用しているヤマイモは自然薯(じねんじょ)、ヤマノイモ、大薯(だいじょ)の三種類である。自然薯は日本では古くから自生し、食用や薬用に利用されてきているが、栽培種として発達したヤマノイモとは別の種類のものらしい。
 「いろどり」20号より
「いろどり」20号より
ヤマノイモは中国の原産で、中国から日本へ渡来したもの。飛鳥から室町時代に栽培が始められたという古いイモだ。この仲間が分化してナガイモ、イチョウイモ、ヤマトイモなどの種類が生じ、多く出回っている。これらは周年出回るが、やはりうまいのは八月からといえよう。
ヤマトイモの球形が団塊状になったのがツクネイモ。白皮の伊勢イモ、黒皮の大和イモ、丹波イモが代表品種で、味がよく粘りの強い高級品で、京都を中心に関西での需要が多い。とろろに最適である。
ナガイモは自然薯の栽培品種で、水分が多く粘りが少ない。煮物や、歯ざわりのよさをいかして生のまま刻んで梅肉と和えものにするが、漬物もよい。埼玉県周辺に多い。
ナガイモの糠漬けは歯ごたえがよく、それほど深く漬からないのがいい。これは知人の料理人の名物料理で、どういうわけか食通の漫画本の『美味しんぼ』でも紹介されている。テレビや雑誌を見て彼の店を訪れる人には、提供しなければならなくなったのだろう。今ではいつ行っても、料理コースの最後のご飯もののときにはこの漬物が提供される。
ヤマイモ類の主成分はデンプンと粘質物(グロブリン様のタンパク質とマンナンの結合したもの)である。この粘質物の性質を利用したのがとろろである。すり鉢の内側にヤマイモをあてて気長に丁寧にまわしてすりおろす。目のあらいおろしがねでおろしたのでは、舌ざわりのいいとろろはできない。このとろろにだし汁を加えたり、卵を加えて淡くのばすのだが、粘性の強いものは、淡くのばしてもいつまでも強い粘り気が残る。
「とろろ汁に麦めし」(ムギトロ)という組み合わせは誰が考えたのか知らないが、よほど忙しい人が見つけ出した食べ方であろう。かつて、東京駅の八重洲北口を出たところに「ムギトロ」を食べさせる店があった。ムギめしのお代わり自由という立ち食いの店だった。友人が「めしをおごる」というので、東京駅で待ち合わせて、その店にでかけた。食事が終わってみると、実に安いめしのおごり方だと関心したことがあった。
一般にナガイモの仲間はデンプン質や粘質物が少ないので、とろろにはあまり向かない。これにくらべて、イチョウイモ、ヤマトイモの仲間は粘質物が多く、とろろとしての利用価値は高い。
ヤマイモ類の酵素の働きは強い。アミラーゼを含むので、デンプンの消化にいいといわれる。また、ヤマイモをすりおろすと短時間でうす黒く変化するのは、ポリフェールオキシダーゼという酵素による。ちょうどジャガイモやリンゴの皮をむくと、すぐに黒っぽく変わるのと同じで、この酵素は空気にふれると作用するのである。
ヤマイモ類は昔から、漢方で「山薬」といわれ、滋養強壮剤として用いられているが、その効力のほどは定かではない。最近は粘質物にガン予防の効果があるともいわれている。